
死の棘 (新潮文庫)
文学とはなにかを深く考えさせられた作品。つまりそれは人間とはなにか、という問いそのものなのだろうけれど、愛と狂気、日常と修羅とのあわいをこれほど克明に彫琢されると、人間とはこうも不完全な生き物なのか、と呆然としてしまう。
物語は等身大のリアリティーに支えられながら進んでゆく。ページを繰るごとに息苦しさばかりが募ってゆく。そして最後まで状況に大きな変化は訪れない。にもかかわらず、読後言いようのないカタルシスに見舞われるのはなぜだろう。
無意識下に働きかける良薬とはこうした文学の毒しかないのかもしれない。
そんな根源的な力を感じさせてくれる作品。
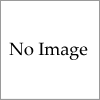
死の棘 [VHS]
この映画のテーマは死の棘ゆえの魂の苦闘、プラスとマイナスの力の拮抗である。原作に伴う漠然とした陰鬱は、醜の深淵を象徴している。妻ミホの執拗な詰問は、絶望への序曲ではなく、迷いの世界から魂の深みへと潜行するためのセラピーである。
始まりは不倫というありきたりの事件だった。苦悩が主人公トシオから妻ミホ、そして子供たちをも巻き込み、家庭をむしばんでいく。不倫を契機に、静かに眠っていた死の棘が呼び覚まされ、しっと・不信・弁解・欺き・不安をまき散らす。これが私たちの日常性ではないか。やがて、愛人を交えた三者の苦闘へと変わる。三者の桔抗において、死の棘が底知れぬ力を発揮する。特攻隊の生き残り、すでに死をかけてしまったトシオの屍は、錨つな解かれ、欲望の大海を漂うかじ取り不在の小舟である。
圧巻は、精神病院からミホがいなくなるシーンである。真夜中の精神病院の裏庭。濁り水をたたえた水槽の底を竹ざおで突きながら、死体を探すトシオ。涙さえ流さずに。その姿には、私たちの魂の邪悪なものすべてが表現されている。だが、死体は見つからない。トシオは不安を覚え、病棟へ駆け戻る。
何とそこには、先回りしたミホが光の中に立っていた。しかし、驚くべきことは、このときのミホの表情である。憎しみや怒りとは無縁の、慈愛に満ちたほほ笑みで迎える。不実の極み、自らの死さえ望んでいた夫に「あなたが私を呼んだから戻ってきたの」という。
そこには暴力性のない、だが、悪をも善へと変容させる驚くべき力の顕現がある。ミホのひたむきな愛によって、自らの魂と徐々に向き合うトシオ。こだわり続けた死の棘が効力を失い、律法という倫理観、正義観、日常性を超えた不思議な愛が現れる。真剣に人を愛する心の回復である。愛は一方通行では成り立たない。対面を避けてきたトシオを愛の応答へと促す。癒しが必要だったのは、トシオの魂だった。こうしてラストシーンへ収斂する。

IN
桐野夏生の小説には、読むとすぐにそれとわかるモデル事件が存在する。
『OUT』の井の頭公園バラバラ死体遺棄事件、『グロテスク』の東電OL殺人事件、『東京島』のアナタハン事件。
そして本作は、島尾敏雄夫妻と敏雄の作品『死の棘』、業界では誰もが知っていた作者自身のダブル不倫事件がモデルとなっている。
現実に題材を取る作家ではあるものの、しかし桐野は現実に取材する作家ではない。
本作の感想に、作家の取材方法がわかって面白かったと表現しているものを散見するが、桐野自身はこの手のインタビュー取材を行ってはいないのだ。島尾敏雄とミホ夫妻に対する子供側からの冷ややかな視線は、島尾伸三本人が、すでに赤裸々に綴っているところであり、桐野はそれを読んだだけであることは明らかである。
つまり、物語の後半、劇的に真相が明かされていく過程は、娯楽小説としてのスタイルであり、桐野の創作なのだ。もちろん、彼女の不倫相手も死んではいない。
娯楽としてのサービスが充分であり、巧いとも言えるが、甘いともいえる。
良くも悪くも、本作は『OUT』の裏面、対になる作品であり、『OUT』が最終局面で甘く緩い方角に流れたように、また作者のデビュー作の特徴である、「主人公だけに、とっておきの秘密をべらべらと喋る初対面の相手」という女性ミステリ作家にありがちな大きな欠点も抱えており、その欠点の分量込みで、桐野の出世作『OUT』の完全な再現となっている。
(事情を知らない方が本作を『OUT』と無関係と断じているが、桐野は不倫相手と『OUT』を作ったのであり、その創作に至る道筋が本作には書かれている。)
小説家が小説家を主人公にした小説は非常に多く、その大部分が作者の狭い世界の狭さを見せられているようで興ざめなものだが、本作は、その狭さをすさまじい深さで補い、充分に必然性のある激しい作品を作出している。
本作は、桐野の最高傑作には絶対にならないが、次へのステップとして大きな意味がある重要な作品であることははっきりしており、読むべき一冊であることは明らかだ。

ナニカアル
実在の作家の幻の作品か?という設定がどれだけ魅惑的でしかしチャレンジングなものであるか、文学を志す者や小説を愛する者には分かってもらえると思う。私の5つの★の一つは先ずこの点にであり、逆にこの点や林芙美子や作品の描かれた時代背景に興味や知識のない方なら、絶対につけない★とも言える。
私自身、作者が林芙美子の文章を書ききるための労苦やその成果を十二分に受け止める素養があるわけではないが、平たく言えば「昭和の前半の桐野夏生の過激版」が描く世界と勝手に解釈して、本作に一気にのめり込んでいった。
この作品が作者の過去のテーマや内容に似ているとの評は表面的に過ぎる。作者は、己に通底する「ナニカアル」を芙美子に感じたからこそ、この作品を描き切ったと解する方が、この作品を素直に深く味わえるだろう。つまり、冒頭のような頭で読むアプローチが出来ずとも、他の桐野ワールド同様に、本能で感じ、肉体に味あわせることで、改めて頭の中に読むべきナニカが現れるはずだから。
とにかく読み切った後に己の中のナニカアルが感じられたなら、虚実の狭間にこそ本当のナニカがアルであろう本作の、実在の人物や史実を調べていって欲しい。そこにないものに、芙美子は、そして、作者は何を感じたのか?
実に味わいの深い作品だと思う。一読して★を5つにするのではなく、★が5つになるまで読み重ねる作品ということ。




![Keyboardmania (PC) - Memories [Perfectplay] KEYBOARDMANIA](http://img.youtube.com/vi/UcsE3QOs_r4/2.jpg)

